ヴァイオリン覚書♪4年10ヶ月~170回めのレッスン ― 2010年01月12日
昨年、いい加減伸びて枝毛だらけになっていた
お腹くらいまでのロングヘアを
チェロの発表会後いっきにリセットして
米倉涼子風(by会社の子※あくまで他人の感想ですヨ)になり
気持ちも雰囲気もリニューアルして臨みます!(笑)
しかし、鏡開きも済んでしまった今、うっかりして
いきなり先生へ新年の挨拶を忘れてました…あらら。
レッスンはト短調のスケールのスラー1つで2音と4音バージョンから。
音程は安定してきたのですが
やはりスラー1つの最後の1音の音量が
弓の速度の都合で大きくなって飛び出てしまうらしく
注意されたものの…
「ま、これは永遠の課題ということにして次いきましょう」
とおまけ合格をもらえました。
何年経ってもこの課題はなかなか克服できませんね…。
次は4thポジションの練習曲。
一音とびで上がったり下がったりする曲です。
音程に気を取られて、弓が…これもいつも言われることですが
お尻が減衰して萎んだ音になってしまうため
最後まで吸いつけて一定の音量を保って返すよう注意され
何度か弾き直してある程度改善されたところでOKをもらいました。
もうひとつの練習曲はD線とA線だけ使って、
各弦の4thポジションから色んなポジションへ
一音とびのフレーズでジワジワ移って上がったり下がったりする
ポジション移動のトレーニングです。
これも音程が非常にとりづらいため
音程に気を取られると左手の指先につい力が入り
弓の方がおろそかになってまた音が一定になりません。
何度か色んな課題点を注意されながら弾き直して
これも完全とは言えませんが今後の課題ということで
OKをもらいました。
最後はエックレスのソナタ。
その前に先生からひと言。
「今日のレッスン、ちょっと早めに切り上げる?」
実はこの後先生に、課外授業(笑)を頂いていたのです。
「その方がありがたいかもです」
「じゃあ、10分早く切り上げましょう。その分は
またの機会に埋め合わせしますね」
ということになり、エックレスのソナタの第一楽章を
1回通して弾きました。
「うーん、ヴィブラートが硬いなぁ…。
手のひらだけでかけてるので、もっと指の関節を柔らかく使って
なめらかなヴィブラートを使えるように。
今日はその辺も観察してきてね。じゃあ、いってらっしゃい」
「いってきま~す♪」
ダッシュで楽器を片づけて、ダッシュで課外授業へ(笑)
というわけで、次項へ続きます~。
ヴァイオリン覚書♪読売日響名曲シリーズ 名古屋公演 ― 2010年01月12日
レッスン一週間前にヴァイオリンの先生からメールを頂き
読売交響楽団の公演にご招待頂いたのです♪
ヴィオラの楽団員さんが、先生の学生時代の同級生なんです。
以前もご招待いただきましたが、今年は早々ラッキー♪
でもレッスンは19:00終了、コンサートは19:00開演で、
教室とは違う最寄駅の会場だったので
当然間に合わないのは、先生も承知の上。
演目上、課外授業として相応しい
2番目のヴァイオリン協奏曲から聴けるのがベストですが
1番目のロッシーニ「歌劇〈結婚手形〉序曲」が5分くらいの曲なので、
これまたレッスンをきっかり時間まで受けてたら
間に合いません。
というわけで、先生はそれらを考慮して
10分繰り上げレッスンとしてくださったのでした。
レッスン後、ヴァイオリン背負って小走り(体力なくてダッシュできず…)
で向かったら、ちょうど1曲目の演奏中にホールへ到着できました♪
ヴァイオリンをクロークへ預け、
息を整える余裕もあって、ホッ(笑)
本日の指揮は読響正指揮者の下野竜也さん。
勢いのある指揮で、わりと好きです。
で、課外授業の一番のお目当て曲は、
ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲♪
ドヴォルザークといえばチェロ協奏曲があまりにもメジャーで
ヴァイオリンはちょっと影が薄いのですけど
私は中欧の民族的な匂いがプンプンしてて好きな曲です。
でもまともに通して聴いたのは
ネットラジオのライブ放送を録音したソリストがヒラリー・ハーンの演奏くらい。
彼女は高音がちょっと冷たい響きなので
中欧の冬の寒さが厳しい~という演奏だったのですけど、
本日のソリスト、リザ・フェルシュトマンさんは
初めて聴く方なので、どうかな~???
と、わくわくしながら聴きました。
ドヴォコンVn、ドヴォコンVcで出だしが静かなのとは対照的で
ズダダーンッ!てなってカッコいいんですよね!
そこからすでにテンション上がっていました(笑)
激しい冒頭を受けて、高音からドラマティックに入る
ヴァイオリンソロはどうだったかというと…
高音にとても伸びと艶のある演奏でした。
音のお尻はさっきレッスンで注意されたばかりの私と違い
まさにしっとりと弦に吸いついてる感じで
高音の響きもキーンと来ず、マットでした。
逆に低音の響きはちょっとオケに負けて弱いかな~?
という印象を受けましたが。
全体的には、リアクションが大きい演奏スタイルの割に
音は安定していて感情に入りすぎず冷静で
カデンツァもリズムを大幅に狂わせたりせず
ドヴォルザークの庶民的というか…生活感というか…
人間の住んでいる日常の景色やら温度感が伝わってくる
安心して聴ける演奏でした。
途中から、ヴィブラートもちゃんと観察しなきゃ!
と思って目を凝らしましたが…
曲調が曲調だけに、フィンガリングが速すぎて
よくわかりません…。
コンマスもチェックしましたが、だいぶ上の階の席から
覗き込んでいるため、角度的にヴィブラートは
よく見えないんですよね…残念。
チェロの動きも忘れずチェック。
でも、私のチェロの先生と違って、読響のチェリストさんたちは
わりと冷静で穏やかな演奏スタイルです(笑)
2楽章が終わった辺り?で拍手が起こったので
「あれ?」と思いつつもつられて拍手してしまいましたが
やっぱり途中でした(笑)
ヴァイオリンソロの歌うように軽快な高音で再スタート。
素人が弾いたら確実に
ヒステリックな鳥の鳴き声みたいになりそうな難しい旋律ですが
やはりリザ・フェルシュトマンさんの高音は落ち着いて聴けます。
その他には、フルートとか、管の響きが綺麗でした。
よく鳴っていて、弦とのバランスもよく、大変心地良かったです。
アンコールはバッハの無伴奏パルティータ3番のプレリュード。
これは昨年、大好きなヴァイオリニスト、アリーナ・イブラギモヴァの
CDで堪能したばかりの曲だったので
それと比べると…協奏曲を弾ききった後ということもあり
ややフィンガリング、ボウイングに乱れがあって
やはりアリーナに軍配があがってしまうのですけど
どちらかというとアリーナ寄りの、高音に温かみのある
素敵な音色ではありました。
そんなわけで、ゆったりとした気分で楽しめた
聴き応えもたっぷりのヴァイオリン協奏曲の後が
これまた楽しみでした。
オペレッタで著名なスッペの、かなりマイナーな序曲集です。
★序曲〈ウィーンの朝・昼・晩〉
★喜歌劇〈怪盗団〉序曲
★喜歌劇〈美しきガラテア〉序曲
★喜歌劇〈スペードの女王〉序曲
初めて聴く曲ばかりでしたが、これが楽しかった!
ウィーンフィルのニューイヤーコンサートを思わせるラインナップは
いずれも軽快で、爽快感があり
演奏するオケもノリノリですが、こちらもノリノリになれます(笑)
それぞれ違う劇の曲ではあるけれど
通して聴いてひとつの物語みたいにも感じられる
見事な選曲でした。
また、それぞれの楽器の見せ場もあって
オケによる新年の挨拶にピッタリな感じ。
〈ウィーンの朝・昼・晩〉では、チェロのソロパートがたくさんあって
チェロ学習者としては聴き応えも満点。
共鳴する弦の響きで全体の盛り上がりも最高でしたが
ここでも管のソロが綺麗…。
弦の激しさを宥めるような優雅でゆったりとした響きや
すーっっと一涼の風を運ぶようなところは
曲の構成もさることながら、
演奏者それぞれがバランスよく素晴らしかったです。
ただひとつ、気になって仕方なかったのは
ソロコンサートマスターの隣のコンマスの動き!
ヴァイオリン協奏曲の時はソリストの陰になってて
見えてなかったのですが
序曲に入ったら私の席からがっつり見える位置で
半球1/4の空域は確実に制されてました(笑)
序曲の構成にはギャロップのリズムも入っていますけど
ギャロップを弾くというより、まさにご自身が実際
椅子から前のめりに転げそうな勢いで
ギャロップしてらっしゃいました(笑)
コンマスだから演奏レベルはオケの中でも上位なのでしょうが
あれだけ激しく揺れたら、ソロコンマスの視界にも入るし
かなりうざいんじゃ…(笑)
途中からあまりにも気になって演奏に集中できず
意識的に他の楽器を見るようにしたほどです(爆)
演奏は堪能しましたが、ある意味凄いものを見て(笑)
無事(?)予定プログラムを終了した後で
下野さんから新年のご挨拶と、
名古屋出身の団員の紹介があり、
オケに親しみも湧いたところでのアンコールは
これでもかといわんばかり、スッペの「軽騎兵」序曲でした。
唯一知ってる曲でしたが
私的にはプログラムの序曲の方が構成も演奏もよかったです。
新年初めてのクラッシック鑑賞はこうして幕を閉じました。
結局ヴィブラートの観察はあんまり出来ませんでしたけど(爆)
スッペの序曲たちのような速いフレーズの曲を
軽々とこなせるようになりたいな~と思ったり。
今年も色々な音楽を聴いて、コヤシにしたいです。

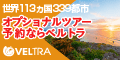
最近のコメント