ヴァイオリン覚書♪5年11ヶ月~206回めのレッスン ― 2011年02月08日

換えとくべき?と思いつつ…結局一週間経ちました(爆) メンドーだしぃ…ボソ。
A線、多分張り替えてから1年以上は経ってると思うので、経年劣化でもおかしくはないのですけど、この引っかいたような感じから察するに…例の重音スケールで一生懸命、弦上に指をキープしようとしてなけなしの爪で引っかけてるせいっぽい…。
なんとなくA線だか何線だか、ツルツルすべる気がした(いや全弦、気のせいじゃないだろう…)ので、弓に松脂だけは塗ってきましたが、今日も弦はこのままでレッスンいっちゃいました(爆)
ケチってこともありますが、安ヴァイオリンなのでペグがものすごく硬くて、一度緩めたら最後、調弦して頃合のよい場所に留めておくのが大変なのですよ…。大変労力と根気と時間がかかるのです…。
今、特に右手首痛めてるので、なるべくその作業をしたくないな~…なんて…。
そんなわけで、危うく(笑)レッスンスタート!
っと、レッスン前に先生から振替レッスンのお話があり、3回分でしたので、私の記憶は間違いございませんでした。よってしばらく毎週火曜がレッスンになりますので、ちょっとハード…。
ウォーミングアップにハ長調の2オクターブスケールを単音速めスピード、同じ速さで4音1スラーで弾いてから、重音地獄へ…。
今日も最初から譜面どおり重音で始めましたが…前回同様、数音で撃沈したので結局バラして弾くことに…進歩してないな…くすん。
ハ長調 重音3度で2オクターブスケール

が、譜面どおり2音一度に正確な音程を捉えるためには、バラして弾いてる時のように最初の音に対して3度の音程を探るのではなく、指の開きの狭い、広いという間隔で覚えていくそうです。
ハ長調 重音6度で2オクターブスケール

ハ長調 重音8度で2オクターブスケール

いずれにしても重音で譜面どおりに鳴らすことが最終課題…。
なかなかその領域には達せないので、これが限界と感じたらしく、
「3度は一番難しいのでなかなか安定しませんけど、他は音程も響きもかなり安定してきたので、これはこのくらいにしましょうか…また戻ってもいいし」
と先生から申出されました…。ははは…。
宿題としてはいったんキリをつけますが、憧れの曲を弾けるようになるためには、絶対に必要な技術なので、自習では最初にちょっと弾くようにして、徐々に慣らして行こうかなと思います…!
次回は違う調のスケールや練習曲をやることになり、ポジション移動の練習曲へ。
2ndポジから4thポジへの移動などがあり、音程を取るのがちょっと大変。でも2ndポジさえしっかり捉えれば、わりと流れで弾けるので、1回弾いて、速度アップして弾いて、伴奏君と合わせて、すんなり合格。
身についた技術とそうでない技術の差が、明確に表れてきた感じですね…うーむ。
次はダブルストッピング(重音)の練習曲。ダブルストッピングもブリッジしてないのはわりと大丈夫になってきたので、1回弾いた印象では、音程よりむしろ弓手の圧力が2弦にちゃんと乗ることが課題。頭でどちらかの弦が鳴ってない時がちょこちょこあって、途中から2弦鳴ったりする感じなので、弓圧をしっかりキープするため、もっと腕からしっかり弾いて全弓使うように言われ、2回めを弾くと…
「#の音程がすべて下がりぎみになってしまったので、もう少し上げて弾くと重音の響きが綺麗になります。あとは弓手に神経を使ったら、左手にも力が入ってしまいましたね~(笑)バランスよく捉えられるようにしましょう」
とのことでリベンジになりました。片方に気を遣うと、出来てたとこがダメになる~~っ!うがーっ!
最後にパッヘルベル『カノンとジーグ』の「ジーグ」第1ヴァイオリンパートを伴奏君、先生の第3ヴァイオリンと合奏しました。
第1ヴァイオリン、実は休符の小節が多く、第2、3ヴァイオリンよりも弾くとこが少なくて、覚えるのは楽でした。が、休符から入りのタイミングが小節の半ばからだったりするので、自習では自分の頭でカウントしたり、第2か第3ヴァイオリンの旋律を歌ってスタートして、入りのタイミングをちゃんと練習してきてたのですが…
第2と第3の音が重なると、カウントが乱される…!まさにカノンのキモ!
それで1回目は中盤で入りのタイミングを間違えてしまいました…(爆)
最後に中盤から弾き直して、タイムアウトになったので、レッスン終了。
先生からの指導は
「出だしのレは第1ヴァイオリンが加わった事がわかるように、もっと勢いよく、ヴィブラートを使ってしっかり音を出すようにしましょう。後は全体的に付点のリズムがちょっと甘いので、もっとリズムをしっかり捉えて歯切れ良く弾くようにするといいですね」
とのことでした。
次回はこれを仕上げでもう1回見てもらうことになり、新しい曲へ…とのことだったので、すかさず私
「先生!これ!これ(J.Sバッハ『主よ人の望みの喜びよ』)がやりたいです!」
と進言。先生も
「ああ、これもいい曲ですよね~♪じゃあ、これにしましょう!ジーグを1回弾いて、いけたら次回からこれに入りますので、譜読みをしておいてください」
と仰り、宿題に決定~vvvうっしゃ!
これでチェロとばよで並行して同じ曲をレッスンする運びになりました!
あ、先生にはチェロの事は相変わらずオフレコ…(笑)
いう必要が出来た時にカミングアウトしようかなと思います。

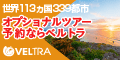
最近のコメント