ヴァイオリン覚書♪6年9ヶ月~241回めのレッスン ― 2011年12月13日

今年も蕾一杯♪これからまだまだ咲きますよ~(*^^*)vvv
肥料とか、ぜんぜんやってないのですが、腐葉土が結構いい栄養になっているのでしょうか?
ただ病気になるとどんどん進行していくので、がっつり切り戻さなければなりません。2年位前に切り戻して、まだ以前の大きさには戻っていませんので、病気に耐えて育ってほしいです。
さて、10日ほど前に全弦交換してから、なかなか安定せず…調弦狂いまくりであせり中なヴァイオリン、レッスンよりむしろチェロ教室の発表会の方が超心配(゚ー゚;Aです!
■ト長調の3度重音1オクターブスケール
今日も2拍弾いて2拍休符で移動で弾きました。
先週あまり練習できなかったせいか、1回目はボロボロ(ノ◇≦。)
先生と、改めて指の間隔を確認してから弾いた2回目は、そこそこの安定感で弾けました。
「休符なしで弾けるようにしばらく続けましょう♪」
■教本P44-13:ニ長調の1オクターブスケールとアルペジオ
弦交換間もなかった前回レッスンでは、弓圧などの感覚の違いがありましたが、慣れてきたのできちんと鳴らしていつもどおり丁寧に弾ける様になりました。そう、もともとスケールとアルペジオ(だけ)は得意なんですよ♪
先生からも文句なしで褒められましたヽ(^◇^*)/ ♪
「うん!とっても綺麗で楽器がよく鳴っていますね!」
■教本P59-1&2:sul.Eのスケールとアルペジオ
やはりスケールは前回より確実に、この弦に慣れてきたせいで綺麗に弾けました。
インフェルド赤のE線、評判どおりやや裏返る傾向にはありますが、嵌った時の音の柔らかさがgood♪
アルペジオも前回同様、ポジション移動の基準になる中間の音を弾いてから次のポジションへ移動する、という変則的な弾き方で、移動がややスムーズでない部分はあったもの、一音一音はしっかり鳴らせました。
「スケールやアルペジオはシンプルだから、その人の音の鳴らし方がよくわかりますけど、ありこさんはとても綺麗に鳴らせていますよ。交換された弦も、前より楽器にあっているみたいですね~音の深みがぐっと変わりましたよ~」
わ~いO(≧▽≦)O 調弦がなかなか安定しないけれど、発表会前に私のヘボ楽器と合っているという先生お墨付きの弦に交換できてよかった♪
■教本P60-3:7thポジ、sul.Dの練習曲
1stポジからいきなり7thポジへ移動する箇所は、やっぱりちょっと苦戦。てか、自習を全然していなかったので当たり前ですね(;´Д`A ```でも最近はあえて自習をせず、レッスン内に感覚で捉えられるようにする即対応力(実力)をつけることも必要かな?とか思ったりしているので、短いフレーズの練習曲、まして初見じゃないものは自習なしでトライもありかと考えているのです。
この曲も3回ほど繰り返せばポジ移動の感覚が掴めたので、これを1パツOKできれば完璧な実力が身についたということなのでしょう。
★マスネ『タイスの瞑想曲』
今日は前回到達できなかった後半から始めるのかと思いきや、頭から伴奏くんと合わせて演奏。
前回指摘されたように、三連符や十六分音符4つ以上のスラーなど、平坦に弾かず、抑揚をつけて弾くようにしました。フォルテからいきなりピアノに落ちるところの切れ目の一音も、前回教えていただいたように…そこへツッコミはなかったので多分弾けていたのだと思います。
今日は八分音符のスラーで下っていく中盤のフレーズで指示が。
「頭の音はもっと溜めていいです。”ターーータララララ”って、”タラララ”へ焦って入らないよう、ダウンテンポぎみで徐々に弱くしていく感じで弾きましょう。後はひとつ気になったフィンガリングが…最後のタラララの0の指は4で取った方がいいですね。開放弦だとどうしても音が飛び出てしまうので、音色を揃えましょう」
フラジオがあったり、弦をいくつも跨いだり、とにかく指が忙しいフレーズなので、技術的にいっぱいいっぱいなのですが…その上にニュアンスを意識しなければならないという…。
「音程は今日、3の指のファ#だけが少しだけ下がり気味になっているので、高めに取るよう注意して弾きましょう」
指摘された部分を意識して中盤から再スタート。
副付点音符の連続で速いフレーズも、今日はようやく伴奏くんの速さになじんできてタイミングがちゃんと合いました。
今日も最後まで通せませんでしたので、次回持ち越し。
起伏の激しい曲はどちらかというと苦手で…ニュアンスを出すのも難しいです~まして技術的にも色々詰まっているし。
でもこういう曲がサラッと弾けたらカッコいいですよね♪
次回レッスンは来週なので…チェロ教室の発表会が優先で、あんまり練習はしてゆけないかもですが、今日指摘されたことは忘れないようにします!

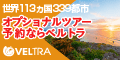
最近のコメント