先日当選した糸のモニターに課せられた亜麻コード使用作品3点が、何とか編みあがりました~。
課題その1:ブレスレット
課題その2:ネックレス
課題その2:自由(ドイリー)
亜麻コードで三作品、製作方法については指定がなかったので、全てタティングレース編みにて作成しました。
他の資材と組み合わせても可とありましたし、このままだと何か微妙な仕上がりなので…提出期限までのセーブとして条件クリアできてるこの画像をいったん保存しておき、ここからは期限を気にせず、またいじります(笑)
とまぁ、かぎ針編みより腱鞘炎を避けられそう?だと思って始めたタティングレースでしたが、不慣れなせいもあって余計な力が入っているらしく、土日で集中的に編んでいたら、かぎ針編みの時に痛めた右手首の内側とは違い左手首の外側を痛めちゃったみたいですぅぅぅぅ。
単純に頻度の問題かもしれませんが(泣)
レッスン前なのに、左手首の外側が筋肉痛のヒドイので…ヴァイオリンの左手使い、特に高弦の高ポジがキツイ……状態でのレッスンスタート。
************************
■教本P:G Majorの2オクターブスケールとアルペジオ
一回目、四分音符単音で弾いたところ
「ほとんど綺麗に弾けているんですが、たまにほんの少しだけ音程が悪くなるところがもったいないので、ピアノのリードをよくきいて、密にすり合わせてみましょう」
と言われ、確かにそんな自覚もあったので、2度目は先生がピアノでリードしてくださる音程をよ~く聴きながら弾きました。
「そうです、そうです♪2回目はとても綺麗になりましたね♪その感じで、指のくっつくフィンガリングなど、音程をより詰めていきましょう」
同様にアルペジオも音程に注意して弾いたのですが、
「高ポジの4の指の押さえが少し弱くて、音の響きが悪くなってしまうので、しっかり押さえてからボウイングするように気をつけましょう」
2オクターブの単純なスケールだけに、音程と音質にはいつも以上の厳密なチェックが入りました~はふ~っ!
■教本P69-7:トリルの練習曲
自習してなかったので、まだフィンガリングや音程感が掴めていなくて、1回目はかなり探って弾いてしまい、トリルをどのタイミングで切るかも迷いがち。
そこはしっかり指摘されましたので、2、3回とスピードアップしながら弾いて、感覚を掴んでゆきました。
★モーツァルト『アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク』第1楽章 第1Vn
前回ざっくり通し演奏したので、今回は頭から前半1/3くらいまで、細かく弾き方などをチェックして頂きながら、小節刻みでフレーズごとに進めていきました。
出だしの3音重音で、その先へ神経をとばし過ぎていきなり低弦の音がスカってしまい、いきなり弾きなおし(苦笑)
【頭から4小節】で既にストップ。
「ロングトーンから弓を戻して弾いて頂いているのはとてもいいんですが、もっと歯切れよく、乗せてアップダウン、特にアップをしっかり引っかけて弾いてください」
言われて意識すれば表れるのですが、移弦が多く、かつてボーイングが”親の仇”と言われた難処(爆)なので、移弦とボーイングの問題が解決された今も、まだツッコミが入りましたよ~~。
アップボウが弱い傾向が続いていますし、毎回注意されるので、いい加減直さないとですね~。
続く最初の【トリルの難処】も、まだ2回トリルに指が馴染んでおらず、1回めでクリアに言っても2回めがフニャッとなっちゃったり…
「トリルが2回とも均一に弾けるといいですね。あと気になったのは1回めのトリルの後の拡張してとる4の音が、微妙にグリッサンドしてしまうので、歯切れよく聴こえるよう、伸ばして押さえきってからボウイングするように気をつけましょう」
2323の指のトリルから21、1~♪に続く、3→拡張4→1と目いっぱい指が広がるところなので、前のトリルに集中しすぎてて手の角度が下がり気味になり、拡張4で上がってこないみたいです。フィンガリング奏して、左手の動きのイメージをつける必要があるかも。
続きの【スタッカートを挟みながら、スラーで前打音が入り、音程が上ってゆくところ】でもストップ。
「前打音の入ったスラーで音数のせいか弓の量を使い過ぎてしまい、次のスタッカートから弾きづらくなっていますので、すべて元半弓以下でおさめるようにしましょう。なるべく少ない弓量でコンパクトにまとめた方が弾きやすいし、綺麗に粒が揃いますよ」
無意識でしたが、もう一度同じところを弾き直してみると…確かに半弓以上使ってて、次のタッタッというスタッカートが元弓で弾けませんので、後半へゆくにつれて乱れてきます…。
しかし意識してもやっぱり微妙に弓を使ってしまう~~!
何度か繰り返し、ものすごーく意識して弾いたら、やっと直りました。
「今の感じです。とても綺麗に弾けていましたので、弓の量をセーブする意識を保ってくださいね」
先に進んでちょっとで、またストップ。
「最後の”シ”は、おさめる感じでそっと弾いてくださいね~。今の感じだと最後だけ飛び出てしまっていますので…」
ここは比較的、音数が少なくて中休み的に気分が楽になるので、ついつい細部が雑に…(苦笑)気は抜けないですね~。
だってここで抜かないと次がまだトリルの連続……
次は2回トリルを入れるという意識で焦りもあってつんのめり気味になってしまい、回数をこなして慣らさないと難しいです…。
そして中盤の【高音域から重音連続部】に突入すると~
「もっとめいっぱいフォルテで弾けませんか?勢いよく、ヴィブラートもしっかり使って鳴らして下さい」
その前までの難所で、すでに力を吸い尽くされた感じ…(爆)
頑張って気力を振り絞ってヴィブラートを使い、重音を鳴らし、先へ進んでまた【トリルの連続】に突入~~
繰り返しのフレーズにトリルが入ってきますが、同じ旋律の粒は全部揃わないとみっともないのはわかっていても…トリルもコンスタンスに2回入らないし、そこが乱れるおかげで前後も曖昧になってしまいます。
「2回トリルを入れる事は問題ないので、そのタイミングが毎回バラバラにならないよう、ここは歯切れよく、常に均一に刻めるようにしましょう」
ただ素早く入れるのは出来るのですが、練習曲でも感じたように、切るタイミングが難しくて…それをちょっと頭で意識しすぎると指が硬くなって動かなくなりますね~。
こころの力みも抜いて、自然にタラタラタラ~っと出来るようにしなければ。
このフレーズを挟んで同じく繰り返される【重音から三連符でスラー】の部分でも
「前後の三連符で入るタイミングが微妙に違うので、両方揃えましょうね~苦笑」
同じリズムを同じように刻むのが、リズム感ないので苦手です…。
「その次のフレーズ(上画像の後半2小節も弾きづらそうですね…フィンガリングを戻し(以前は途中で1stポジに降りていた)ますか?」
次のフレーズのためにはポジション移動しない方がスムーズなのですが、このフレーズだけ切り取ると、ポジション移動しないおかげで移弦が多い、かつスラーやスタッカートで忙しいために、どうも音程が微妙になり、無意識だと以前のクセでポジ移動してしまいます…。
「いえ!なるべく3thポジで弾けるようにしてきます…!」
そして前半で一番の難処ともいうべき、【トリルを含むスラーで上昇しながら、間に短く切る音を挟む】坂道が!!
ここは音程取るのだけでも結構難しく、2回トリルを刻みながら、音形は上がっているものの、ポジ移動は上がったり下がったりしているという複雑な動きをしてくるために、頭の中がカオスです(爆)
「ここもスラーの中にトリルがあって音数が増えると、弓量が極端に増えてしまって後が弾きづらくなっていますので、コンパクトですよ~(笑)」
ちくしょーモーツァルトめ!
コンパクトに細かい動きが多すぎやっちゅうねん!!!
だからキライだっ!!!
それが美しくて感動的なら納得もするけれど、なんか弾き手のポテンシャルを試してる感じばかりが鼻について共感できない…とか弾けない段階で言うのは、負け犬の遠吠えでしかないので、やっぱりキライだけど弾けるようにはなってやる!!
というわけで
「かなり細かい部分まで色々言いましたが、次回は後半へ進みましょう」
との事でした。
2回目の挑戦だと先生もご存知だからこそ、ここまで小節刻みでいっぱい教えていただけるのかも?と思いたいくらい、突っ込みどころ満載なアイネクレッスン。
これだけ細かく指摘箇所があったので、今回は頑張って譜面くっつけてみました。さっくり作っているので、写譜ミスはご了承くださいませ。













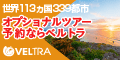
編み物やって、ご飯作って、バイオリンの練習して、ありちゃんいったいいつ寝てるの!?